協力の人間関係
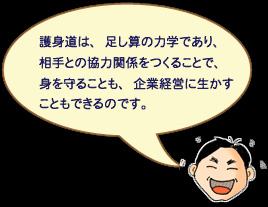
護身道は、自らの身を守ることを本則とした武道である。
だから相手の人間が存在するのであって、一人だけで型だけやっておればよいというのではない。
護身道の人間関係の根本は、相手との協力である。
これまでの武道は、相手と強さを争うことを根本としている。
つまり強い方が勝って、弱い方が負ける。相手が100の力があるのに、こちらが60の力しかなければ、100-60の40で相手が勝つ。
つまり引き算の力学である。
護身道は足し算の力学である。
相手が100でこちらが60なら、100+60の160の力で、侵害してきた相手が倒れるようになっている。
そんなことがうまくゆくのかと思う人もあろうが、実際にやってみれば、ちゃんとそのようになることがわかる。
相手がどんなに重く、力が強くても、それは小さい、弱い方の力と合計して、みんな相手に返ってきて倒されてしまうのである。
この意味で、護身道という武道の根本は相手との協力であるということである。
護身道は相手と自分との間の人間関係をつくることであり、その関係は協力であると言っているのである。
しかし、相手がこちらに不正の侵害をした場合には、相手に倒れてもらうのであって、こちらが倒れるのではないということである。
そのやり方はまた相手の力とこちらの力との協力によって成しとげられるのである。
護身道の人間関係の基本は、次の三ヶ条になる。
1、相手が自分を殺そうとしてきたら、相手が死ぬ。
2、相手が自分をケガさせようとしてきたら、相手がケガする。
3、相手が何もしないのなら、ニコニコして仲良くする。
つまり、人間と人間とは仲良く協力することが本則であるが、時には悪い奴がいて、不正の侵害を加えてくる。
その時は、不正の侵害をやった者が倒れて、やられた方は、いくら力が弱くても、ちゃんと身が守れるようにしようというのである。
世の中には弱い者の方が大部分で、強くて大きいという人は、しょせん少数者にすぎない。
少数の特別の人がいつも勝って、力をふるい、弱い方はいつもやっつけられているような社会ははなはだよろしくない。
護身道の人間関係の根本に立てば、社会の大部分を占める、普通の体の、弱い力の人も、特別な筋肉力の鍛錬をして強くならなくても、自分の身を守り通すことができる。
自分は弱いから強い人にやっつけられはしないかと、いつもびくびくして人生をすごす必要はない。
常に自信をもち、胸を張って人生をおくることができるようになる。
この意味で、護身道はすばらしい人生をつくる脳力開発の勉強と、まったく戦略が同じである。
だから護身道は、脳力開発の武道だといっているのである。
体の動きで、脳力開発を身につけることができるわけである。
企業経営でも、強いもの弱いものがあり、弱いものは常に、強いものにやっつけられはしないかと、びくびくしながら働く人がある。
これは人間関係を常に敵対的なものに受け取り、相手との力の差で自分が負けると思うからである。
引き算の力学で対応するからである。
いつでも他の企業の人たちとの協力関係にもってゆくように手と足と口を動かしておれば、相手が強ければ強いほど自分との合計の力が大きくなり、仕事に有利なわけである。強い相手が自分に不正の侵害をすれば、相手が倒れるとなれば、やられはせぬかという心配でウロウロすることもない。
足し算の力学を企業経営にもちこめば、これができるのである。
協力の人間関係をつくるのは、日本人は有史以来何千年の歴史的伝統をもっている。
歴史の記録が出現した時から、日本か灌漑水田による米作を生産の中心にすえてきた。
水路をつくり、田植えをし、秋の暴風雨のこないうちにす早く刈り入れをするなどという一連の活動は、すべて多勢の人間の協力活動がなければできない。
その脳反応の伝統は今日でも生きていて、何をするにもすぐまわりの人と相談してするようになっている。
根回しなどというがこれはその一つの表現である。
欧米人はその反対に自己主張の個人主義の哲学を人間関係の根本にすえている。
中近東に出発した人類は水があるところに草が生え、草を食べさせて羊が飼え、羊に頼って生活をたてた。
水はわずかしかなく一定している。
他人に入り込ませる余地はない。
人間は生産力ではなく、消費者にずぎず、羊が生産力なのである。
他人が入りこんできたら、自分が死なねばならぬ。
自分が生きるためには、他人が入り込まぬように水を守り、入りこむ他人を殺すか追いはらわねばならぬ。
日本人の脳の反応と、欧米人の脳の反応とでは、ここのところが根本的に違っている。
その違いを認識し、うまく対処しないと、仲良く出来ない。
護身道は体の動きそのもので、この歴史的伝統をもつ協力の力学を生かし、人間関係の根本にすえようというのである。
そして日本の企業もまた、この根本に立ち返って人間関係をつくってゆけば、大きな発展をもたらすことになろう。
| 〜城野宏論文集より〜 |
shop info.
copyright©2013 all rights reserved.